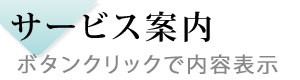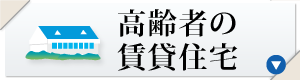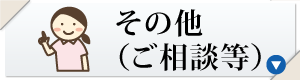東和グループのご紹介
ごあいさつ
当グループは約50年前の「小林医院」開業に始まり、その5年後の社会福祉法人東光会設立から、「医療と介護」の両方を一体化して運営することで、高齢者を中心とした地域の方々に適切な医療・介護サービスを切れ目なく提供することを目指してきました。
現代は「地域包括ケア」の時代であり、「『医療介護の一体化』なんて現代では当たり前だ」と言われそうです。また、理念の「どなたにも(その方にとっての)最良」をとか「あなたの尊厳を守り」などというのも、ほぼすべての医療機関・介護事業所が言っています。なぜなら「医療介護の倫理」であり、資格制度上の義務であり、介護保険制度等の理念でもあるからです。「基本」・「常識」であり、我々の義務です。
では、「医療と介護がスムースに一体的に運営されているか」、「それぞれの方のベストの選択肢は何かを適切に考えて対応し提案できているか」、「それぞれの方の尊厳を最大限に尊重する対応ができているか」といえば不十分なことが多々あります。
「在宅での療養・介護」の実態を病院の担当者がよく知らないので調整が不十分で、準備不足で退院できない。「適切な医療・リハビリを行えばなおる・良くなる」事を知らない介護事業所が病状悪化・ADL低下を「お手伝い(介助)」だけで対応してしまい、「なおる・良くなる」はずだった方の病状が改善困難になるまで放置してしまう。知識・経験・技術が不十分なまま「どうせ歳だから仕方ない」・「どうせ認知だからムリ」などと決めつけて最善でない対応をしてしまい、自分達も苦しみながら、高齢者の方も不幸にしてしまう等が多々あります。
「うちは特別で完璧です」などというつもりは全くありませんし、言えません。我々の職員も知識・技術・経験不足が少なからずあり、日々、指導や教育の難しさを実感しています。だからと言って「これが‘現実’」とか「だって仕方ない」と言い出すと、知識・技術・経験不足に目をつぶり、さらなる劣化が急速に進行してしまいます。なので、職業倫理として不断の努力が義務となっており、法的にも医療介護は「高度の善管注意義務」が求められています。
現代日本は、これまでの日本人が経験したことの無いような急速な人口減少社会に入っています。その中で、高齢の方々へ向けられる視線がしばしば冷淡であることを感じるとともに、我々全員が「いずれ行く道」である事を忘れているのではないか、「自分自身がそんな扱いをされたいのか」と言いたくなります。高齢の方もそのような風潮を感じられるのか、「長く生きすぎた。早くお迎えが来ないかと思う」などとさみしいことをよく言われます。
「尊厳死」・「無理な延命は不要」などという言葉が日常的な用語になっています。「施設・病院に行くとロクな目に合わない。在宅で死にましょう」というキャンペーンをしておられる方が医師にもいます。高齢者医療・介護を日々の仕事とし、「高齢者でも適切な医療・リハビリ・ケアでなおる・元気になる事が多い」・「治らない病気・改善困難な病態があっても、日々の苦痛を軽減して、より穏やかにすごすための技術や知恵はたくさんある」ことを実感している者としては大変「モヤモヤ」します。
「とにかく長く生きるのがスバラシイ」とか、「病院や施設ですごすのが一番幸せ」などというつもりはありません。それぞれの方の価値観・ADL・基礎疾患の性質や医学的知見等を総合的に判断して、「それぞれの方の最善」を考えて提案するのが医療介護の基本であるというだけの事です。必要もないのに「入院したい・入所したい」という方はおられません(まれにおられますが、それ自体が「病気」のような不安の強い方です)。だからと言って「最善でない医療や介護」を「止むを得ない・避けがたいもの」と決めつけて、「だから医療や介護は害悪。そんなものには近寄らず、早く死ぬべき」などと言い出すのは間違っています(特に医師や医療機関、介護施設が言い出すとかなり危険なのは歴史や日々の現実が証明しています)。また、「在宅医療・介護でないと不幸になる」という価値観の押し付けのために介護者や被介護者が追い詰められ高齢者虐待や共倒れになりそうな事案を見ると、「医療や介護を『ご自分の都合にあわせて』利用すれば、もっとしんどくなくすごせます」とお伝えすべきと感じます。入院したからといって、ずっと入院する必要はなく、むしろADL低下を生じないように短期での退院が目標になります。「必要な時にだけ施設を利用」が地域包括ケアの時代では「目標」です。「まずは試してみて、合わなかったらまた考えましょう」で良くないでしょうか。「答えは一つではない」ことを分かる事が現実を生きる人間の智慧ではないでしょうか。
「老いる事」・「病になる事」・「死ぬ事」と共に、「生きる事」自体が「人間ごときには思うようにならないもの」と自覚することによって、「心を落ち着けて、難しい現実になるべく的確に対応できるようにしよう」というのが、「方丈記」や「平家物語」のような仏教文化の影響を受けた古典を義務教育でも学ぶ、東アジア文化圏の国である日本人の古来からの智慧ではないでしょうか。また、キリスト教文化の中で成立した伝統的な西洋医学の倫理観も、「医師が生きる価値の是非に踏み込むと重大な害悪をもたらす危険性が高い」として、「医師は生死の是非には立ち入らず、ただひたすらに患者さんによりそって身体的・精神的な苦痛を軽減することに最大限の努力を行え」としています。
人間は苦痛が強いと「早く死にたい」と思ってしまうようで、重症の心不全でゼイゼイと苦しそうに息をしながら「死にたい」と言っていた方が、治療が奏功して楽になると、ニコニコしながらおいしそうにご飯を食べておられたりします。私の父は癌で死にましたが、死の5年前に手術を受けた直後、「今後の仕事のことを考えたら色々心配でつらい。いっそ早く死にたい」と言い出しました(医学的に考えると早晩再発で亡くなる可能性が高かったのですが)。そうかと思えば、その5年後に予想通り再発した際は、「尊厳死だ」と言っていたこともある人間が、「次の正月までは生きたい」と言いながら最後まで必死に食事をして12月29日に力尽きました。
医学的・生物学的に言えば人間の生物としての寿命は大体きまっているので、「お迎え」は急がなくとも、遠からず、誰にでも必ず来ます。その時は、「嫌だ。後にしてほしい」と思っても聞いてもらえません。「人間ごとき」は余分なことを考えず、ただひたすらに、できることの中で最善を目指すのが良いと思っております。それぞれの方の価値観、人生観等を最大限尊重するのが我々の仕事だと考えております。お困りのことがありましたら、何でもお気軽にご相談ください(また担当者の対応が不十分だとお感じになった場合は是非とも教えてください。事実確認の上、適切に指導いたします)。
東和グループ 小林芳人
私たちの理念
私たちは、あらゆる方々にあったサービスを提供することによって地域社会のセイフティネットの一翼を担い、それを発展させていくことを使命としています。
皆さんに信頼され、愛されるために次のことを理念としています。
- どなたにも最良のサービスをさせていただきます。
- あなたの尊厳を守り、より自立した生活を支援します。
- 施設は明るく、事業は透明に。
- 効率の良い経営を目指します。
- 職員は研鑽に努め、互いを生かす職場を。
社会福祉法人東光会

東和グループ 創設者
小林芳治